NHKドラマ『舟を編む』では、登場人物たちが十数年をかけて一冊の辞書「大渡海」を編さんする姿が描かれます。
「大渡海」は物語の中心にある存在であり、登場人物たちの思いや成長が詰まった“言葉の結晶”とも言える存在です。
この記事では、「大渡海」のモデルとなった実在の辞書や、辞書編集の工程、そしてドラマが伝える“言葉を編む意味”について詳しく解説します。
この記事を読むとわかること
- ドラマに登場する辞書「大渡海」の役割
- モデルとなった実在の辞書や編集のリアル
- 辞書に人生を懸けた人々の想いと魅力
ドラマ『舟を編む』の「大渡海」とはどんな辞書?
NHKドラマ『舟を編む』に登場する辞書「大渡海(だいとかい)」は、作品の中で中心的な存在を担う辞書です。
ただの道具としてではなく、登場人物たちの情熱・信念・人生そのものが込められた“言葉の海”として描かれています。
ドラマを通して描かれる「大渡海」の存在感は、視聴者にとっても“言葉の重み”や“辞書の奥深さ”を再認識させるきっかけとなっています。
物語に登場する辞書の役割と存在感
「大渡海」は、物語の登場人物たちが十数年という歳月をかけて編んでいく中型辞書です。
新語から古語まで、あらゆる日本語の用法・意味・使い方を網羅し、“言葉の海を渡るための舟”として作られるこの辞書は、まさに作品のタイトル『舟を編む』そのものの象徴でもあります。
主人公たちにとって、「大渡海」は単なる業務ではなく、生き方を賭けるに値する“人生の使命”となっています。
1語1語の定義、例文、語源の確認に膨大な時間と手間がかかることを知れば知るほど、辞書とは“人の言葉を信じるための本”であることが実感されます。
辞書に込められたテーマと象徴性
「大渡海」は、ただの架空の辞書ではありません。
それは、「人と言葉の距離」「人間関係とコミュニケーション」「社会と個人のつながり」など、多くの現代的テーマを象徴する存在として、ドラマ全体に深い意味を与えています。
例えば、「空気で伝わる」「なんとなく察する」といった曖昧な表現が多い日本社会において、「言葉の正しさ」を守るという行為は極めて誠実で勇敢な姿勢です。
「大渡海」の編集を通して、登場人物たちは自分の考えを言葉にする勇気、相手とつながる手段としての“言葉”の力を改めて学んでいきます。
そのため、「大渡海」という辞書は、ただ情報を載せるだけでなく、言葉の未来を信じる“希望の舟”として、視聴者の胸にも深く残る存在となっているのです。
ドラマ『舟を編む』の「大渡海」のモデルとなった実在の辞書は?
『舟を編む』に登場する辞書「大渡海」は架空の辞書ですが、その背景には実在するいくつかの国語辞典の存在が大きく影響しています。
特に、『広辞苑』『大辞林』『岩波国語辞典』など、日本語辞典の代表格がモデルとされており、著者・三浦しをん氏自身が複数の辞典編集部を取材したうえで本作を執筆したことが知られています。
ここでは、「大渡海」に色濃く影響を与えた実在の辞書と、作品との関係性について詳しく解説します。
『広辞苑』『大辞林』などの影響
国語辞典として最も広く知られる『広辞苑』(岩波書店)は、その語数・歴史・信頼性の高さから、日本語辞典の“金字塔”とされています。
また、三省堂の『大辞林』は、語釈のわかりやすさや現代語への対応力に定評があり、用例や語感を重視した記述スタイルが特徴です。
『舟を編む』の「大渡海」が目指すものも、まさにこれらの辞典のように、“現代日本語を網羅し、読者にわかりやすく言葉の本質を伝える”という姿勢に貫かれています。
そのため、作中の用例採集や語釈の推敲などの描写も、実在の辞典編集部の現場と極めて近いリアリティを持っています。
三浦しをんが参考にした実際の辞書作り
原作者・三浦しをん氏は、『舟を編む』執筆にあたり、岩波書店や三省堂など複数の辞書編集部に綿密な取材を行ったと明かしています。
編集者たちの「ことば」に対する異常なまでの執着、用例カードを収集する日常、地味で気の遠くなるような工程などが実際に存在し、それが馬締や松本といった登場人物の造形に落とし込まれています。
特に、劇中で描かれる「一語の語釈をめぐって徹底的に議論する」「実際の使われ方を町中でメモする」といった場面は、辞書編集の現場で本当に行われている作業そのものであり、リアルな職業ドラマとしての側面も持っています。
こうした取材と想像力によって生まれた「大渡海」は、架空の辞書でありながら、現実に存在していそうな“生きた言葉の集合体”として、多くの読者・視聴者の心に残る存在となったのです。
辞書編集の工程はどれほどリアルか
『舟を編む』はフィクションでありながら、辞書作りの工程が極めてリアルに描かれていることでも高い評価を受けています。
一冊の辞書が完成するまでに必要な膨大な作業と、それに関わる人々の労力と情熱。
ここでは、作中に描かれた辞書編集のプロセスが、実際の現場とどれほど近いのかを具体的に見ていきます。
言葉の選定・用例の採集・語釈の作成
まず辞書作りのスタート地点は、「語の選定」です。
時代や社会に合わせて新しく収録すべき言葉を決め、その言葉がどう使われているかを日々の中から拾い集める“用例採集”が始まります。
作中でも、松本先生が小さなカードに用例を記録している姿が印象的に描かれますが、これは実際に辞書編集部で行われている手法そのものです。
続いて、その語に対してどんな意味があるか、文脈によってどう変化するかを徹底的に議論しながら語釈(ごしゃく)=意味の説明を作成していきます。
この語釈こそが辞書の“命”であり、最も神経を使う部分だと編集者たちは語ります。
校正・用紙選び・製本までの道のり
語釈が決まったら終わり、ではありません。
次は何度も何度も行われる校正・校閲の工程へ。
誤字脱字はもちろん、語釈の整合性や文体の統一、表記の揺れなど、細部まで目を光らせる作業が続きます。
さらに、『舟を編む』では紙の選定にもスポットが当てられています。
軽くて薄くて丈夫、インクが裏写りせず、めくりやすい紙を追い求める描写は、実際の製紙会社との連携を必要とする“リアルな工程”です。
最終的に製本・装丁に至るまで、辞書はまさに“工芸品”として完成するのです。
ドラマはこの全工程を丁寧に、誠実に描き出しており、視聴者は「辞書ってこんなに手間のかかるものなんだ」と自然と気づかされます。
その“気づき”こそが、『舟を編む』が辞書というテーマを選んだ最大の意義かもしれません。
ドラマ『舟を編む』で描かれる“辞書に人生を懸ける人々”
『舟を編む』は、一冊の辞書「大渡海」の完成までの道のりを通じて、“辞書作りに人生を懸けた人々”の姿を丹念に描いています。
派手な展開や事件があるわけではないものの、その静かな日常の中にこそ、人の想い・努力・信念が込められており、深い感動を呼び起こします。
ここでは、登場人物たちの視点を通して、“言葉に命を吹き込む仕事”の尊さに迫ります。
馬締光也・岸辺みどりを通して見る辞書編集者の姿
主人公・馬締光也(演:野田洋次郎)は、言葉に対して異常なまでに誠実な人物として描かれます。
寡黙で不器用、人付き合いも苦手ながら、ひとたび言葉に向き合うとなれば数時間でも机に向かい続ける集中力を発揮します。
彼の姿からは、“編集者というより、言葉と対話する研究者”という印象を受ける人も多いでしょう。
一方、辞書編集の世界に飛び込んだばかりの岸辺みどり(演:池田エライザ)は、視聴者の分身のような存在です。
最初は違和感と戸惑いを感じながらも、少しずつ「言葉に真摯に向き合う人たち」の姿に触れ、自らもその価値に目覚めていきます。
この二人の成長と対比が、『舟を編む』という作品を人間ドラマとして豊かにしています。
辞書作りが人生観に与える影響とは
ドラマの中で何度も語られるのが、「辞書作りは、生き方そのものだ」という考え方です。
膨大な時間をかけて一語一語に向き合い、用例を集め、語釈を整えるという地味な作業の繰り返し。
それでも、編集者たちはその仕事に価値と誇りを感じているのです。
辞書編集を通じて、登場人物たちは“言葉が人を支え、つなぎ、救うことができる”という真理にたどり着きます。
そして、言葉の持つ重みと責任を知った彼らは、やがて「自分がどう生きるか」にまで影響を受けるようになるのです。
視聴者にとっても、それは決して他人事ではありません。
言葉を雑に扱うことが当たり前になりつつある現代において、『舟を編む』は改めて“ことばの価値”を静かに問いかける作品となっています。
ドラマ『舟を編む』 × 辞書「大渡海」まとめ
NHKドラマ『舟を編む』は、架空の辞書「大渡海」をめぐる物語を通して、言葉と向き合うことの尊さを描いた作品です。
辞書という地味で静かなテーマながら、その制作過程と関わる人々の情熱は、想像を超える“知のドラマ”であり、視聴者に深い感動を与えました。
「大渡海」は、単なる本ではなく、言葉と人と時代をつなぐ舟として、作品の根幹を支えています。
言葉を紡ぐことの価値を見直すきっかけに
情報があふれ、言葉が軽く消費されがちな現代。
『舟を編む』が描いた「大渡海」の編纂過程は、そんな時代だからこそ、ひとつの言葉に丁寧に向き合う姿勢の大切さを思い出させてくれます。
言葉は人を傷つけることもありますが、同時に人を守り、癒し、つなぐ力を持っている。
その力を信じて、言葉を“編む”人たちの奮闘は、見る者の心にも静かに火を灯すのです。
「大渡海」が教えてくれる“言葉の海”の奥深さ
辞書とは、単なる情報集ではありません。
『舟を編む』が教えてくれるのは、辞書が「時代の記憶」であり、「人間の営みの結晶」であるということ。
「大渡海」という名前の通り、私たちは日々、膨大な言葉の海を渡って生きています。
その海を安全に、正確に、誠実に渡るための道しるべとして、辞書があり、それを編む人たちがいます。
『舟を編む』は、その“見えない仕事”に光を当て、言葉と生きるとはどういうことかを静かに問いかけてくれる名作です。
この記事のまとめ
- 「大渡海」は物語の中心となる架空の辞書
- 実在の辞書をモデルにしたリアルな描写
- 言葉と向き合う人々の姿を丁寧に描写
- 辞書作りの工程や想いの重みを知れる
- 言葉の価値を見直すきっかけになる作品
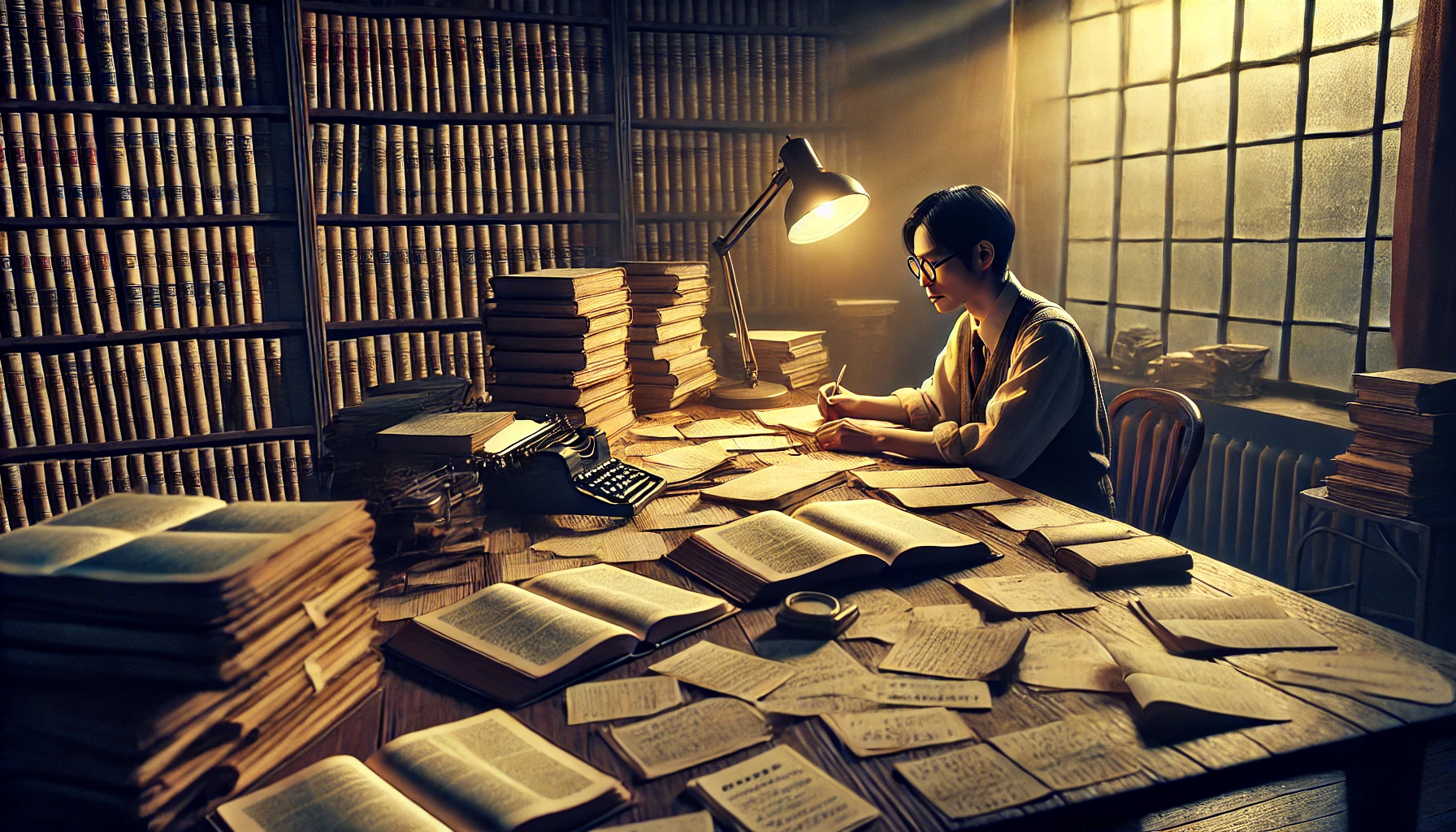


コメント